

チェルノブイリ原発事故で汚染されたウクライナ、ベラルーシ、ロシアの3カ国では、原発事故から5年後に被ばく線量を減らして住民を守るための法律 「チェルノブイリ法」を制定しました。
その詳細が分かるテレビ番組があります。2014年8月23日にNHKが放送した
「原発事故 国家はどう補償したのか ~チェルノブイリ法 23年の軌跡」
日本政府は、年間被ばく線量が「20ミリシーベルト以下なら住んでよい」と決めて避難した住民を帰還させていますが、チェルノブイリ法の第1章 第1条には、放射性物質の汚染地域とされるのは、住民に年間1ミリシーベルトを超える被ばくをもたらし、住民の放射線防護を必要とする地域であると明記しています。そして、その汚染地域を補償の対象にしています。

年間1ミリシーベルト以上被ばくする汚染地域には「移住の権利」が与えられ、5ミリシーベルト以上は「移住の義務」があり、住むことができません。
1ミリシーベルトを超える地域は補償の対象となり、無料で検診が受けられ、薬代の無料化、公共料金の免除、 非汚染食料の配給、学校給食の無料化、非汚染地域での「保養」の旅行券が支給されるなど様々な補償があります。
また、移住をする人には移住先での仕事を探し、住居も提供、引越し費用や移住によって失う財産補償なども行うことで、移住をしやすくしています。

チェルノブイリでは、原発事故から5年後に「チェルノブイリ法」 を制定して原発事故の被害者を救済しようとしてきましたが、日本では原発事故から10年が過ぎても1ミリシーベルト以上の汚染地に「移住の権利がない(補償がない)」だけでなく「20ミリシーベルトまで安全」と政府が勝手に決めて 避難していた住民を汚染地に戻す政策を取り続けています。
–
日本政府のこうした政策に対して、国連人権理事会は何度も問題点を指摘してきました。

政府が定めた年間 20ミリシーベルトの避難基準について「チェルノブイリ事故の強制移住の基準は年間 5ミリシーベルト以上だった。こうしたズレが住民の混乱を招いている」( 2012年11月29日 東京新聞 )
–

実は、原発事故が起こった2011年から福島県民に急性心筋梗塞や様々な病気が増加し始めていました。
原発事故後、福島が心疾患死亡率ワースト1になりました。

【福島県と周辺県の心疾患死亡率が増加】
2010年度 2011年度 増加率 増加数
福島 197.6 226.0 14.4% +28.4
宮城 141.3 160.0 13.2% +18.7
茨城 150.1 165.9 10.5% +15.8
岩手 202.6 219.3 8.2% +16.7
全国平均 149.7 154.4 3.1% +4.7
福島原発事故の10カ月後 周産期死亡率が急上昇
周産期死亡 率(妊娠22週から生後1週までの死亡率)が、放射線被曝が強い福島とその近隣5県(岩手・宮城・茨城・栃木・群馬)で2011年3月の事故から10か月後より、急に15.6%(3年間で165人)も増加し、被曝が中間的な強さの千葉・東京・埼玉でも6.8%(153人)増加、これらの地域を除く全国では増加していませんでした。

国連人権理事会は、 日本政府が福島の避難基準について1年間に浴びる被ばく線量を20ミリシーベルトとしていることに対して「科学的な証拠に基づき、年間1ミリシーベル ト未満に抑えるべきだ。健康を享受する権利を守るという考え方からは、年間1ミリシーベルト以上の被ばくは許されない 」と明確に勧告しました。

福島事故 国連人権理 報告書
健康である権利侵害
(2013年6月22日 東京新聞)より抜粋
5月27日にスイス・ジュネーブで開かれた国連人権理事会で、福島原発事故後の健康問題に関する調査の報告があった。特別報告者、アナンド・グローバー氏の報告と勧告は、日本政府にとって厳しいものだった。
…健康調査についても不十分だと指摘。特に子どもの健康影響については、甲状腺がん以外の病変が起こる可能性を視野に、「甲状腺の検査だけに限らず、血液や尿の検査を含めて全ての健康影響の調査に拡大すべきだ」と求めた。
日本政府が福島の避難基準について1年間に浴びる被ばく線量を20ミリシーベルトとしていることに対しては、「科学的な証拠に基づき、年間1ミリシーベル ト未満に抑えるべきだ」と指摘。「健康を享受する権利」を守るという考え方からは、年間1ミリシーベルト以上の被ばくは許されないとした。
–
国連人権理事会から厳しい勧告を受けても日本政府の態度は変わりませんでした。
それどころか、国連勧告から3カ月後に安倍首相は オリンピックを招致するため国際オリンピック委員会(IOC)総会で、福島原発事故による健康への影響について、「今までも、現在も、将来も問題ないと約束する」と発言しました。
その発言から2カ月後、原子力規制委員会も安倍首相に同調するかのように「年20ミリシーベルト以下は健康影響なし」と発表。被ばく対策は進まず、逆に避難した住民を「20ミリシーベルト基準」で放射能汚染地に戻す政策を強引に進めはじめました。

この話を聞いたドイツの連邦放射線防護庁の職員はとても驚いて「本当か?それは事実か?本当に年20ミリか?!子どもも妊婦もか?!」と何度も確認した後に「日本の国民は、それを受け入れたのか?! ドイツの国民は、そんなことは許さない」と驚いた様子をドキュメンタリー番組が放送しています。
放射能汚染数値が高い地域では、白血病や悪性リンパ腫も増え始めていました。
この「20ミリシーベルト基準」が異常だということは誰にでも分かります。
–
◆原発事故前の基準は、年間1ミリシーベルトでした。
–
◆日赤の「原子力災害時の医療救護の活動指針」には「救護活動中の累積被ばく線量は、1 ミリシーベルト(mSv )を超えない範囲とします」と明記しています。
–
◆病院のレントゲン室など「 3カ月で 1.3mSv (年間換算では5.2 mSv )を 超えるおそれのある区域」は、放射線管理区域とされます。18歳未満の就労が禁止され、飲食も寝ることも禁止されます。
–
◆原発で働く作業員が白血病になった場合の「労災認定基準」は、年5mSv 以上の被ばくです。(累計5.2ミリシーベルトで労災が認定されている)

◆原発作業3カ月、20年後に白血病判明
5.2ミリシーベルト被曝 労災認定の男性語る
(2013年8月5日 朝日新聞)
政府は、大人ですら5ミリシーベルトの被ばくで 白血病になる可能性があると認めているのです。
–
国連人権理事会は 「年間20ミリシーベルトではなく1ミリシーベルト以下」にするよう 繰り返し 勧告しています。

◆子ども帰還見合わせ要請 国連報告者「年間1ミリシーベルト以下に」
(2018年10月26日 東京新聞朝刊)より抜粋【ジュネーブ=共同】国連人権理事会で有害物質の管理・処分などを担当するトゥンジャク特別報告者は25日、東京電力福島第一原発事故で避難した子どもや出産年齢の女性について、事故前に安全とされた被ばく線量を上回る地域への帰還を見合わせるよう、日本政府に要請する声明を発表した。
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部の担当者は声明に対し「非常に一方的な情報に基づいており遺憾だ。風評被害にもつながりかねない」と批判した。
福島では避難指示が解除された地域から住民の帰還が進んでいる。日本政府は被ばく線量が年間20ミリシーベルト以下を解除要件の一つとしているが、トゥンジャク氏は事故前に安全とされていた年間1ミリシーベルト以下が適切だとの見方を示した。
声明は、日本政府には「子どもの被ばくを防ぎ、最小限にする義務がある」と強調した。
また、原発事故の避難者にとって、住宅無償提供の打ち切りなどが「帰還への多大な圧力になっている」と指摘した。


こうした国連人権理事会の勧告を 日本政府が 無視し続ける中で さまざまな病気が増えてきています。
南相馬市立総合病院が主要な病気の患者数を公表
(2018年10月に公表: 2010年~2017年の年次推移 )



上記データの一部を分かりやすいグラフにしました。



ここまでは南相馬市立総合病院の「患者数」データで、以下は政府統計の「死亡率」データです。
2015年 急性心筋梗塞の死亡率
男女とも福島県がワースト1
厚生労働省が2017年6月に公表した都道府県別の格差。人口10万人当たりで年齢調整をした死亡率で比較。2015年では男性では最も高い福島県と最も低い熊本県で4.03倍。女性では最も高い福島県と最も低い秋田県で5.00倍の格差があった。 (原発事故が起きた2011年以前の急性心筋梗塞は、2000年と2005年のデータでは、福島県は男女とも5~9位)
◆「心臓病」の地域格差 データでみる あなたの市区町村は?
(2017年8月4日 日本経済新聞)から抜粋心筋梗塞、予防と迅速な治療が生死を分ける
血液を全身に送り出す心臓の状態が悪くなる心疾患は、日本人の死因ではがんに次いで2番目に多い。厚生労働省が2017年6月に公表した都道府県別の格差もみてみよう。人口規模が大きいため人口10万人当たりで年齢調整をした死亡率で比較しており、2015年では男性では最も高い福島県(34.7人)と最も低い熊本県(8.6人)で4.03倍、女性では最も高い福島県(15.5人)と最も低い秋田県(3.1人)で5.00倍の格差があった。
都道府県別の急性心筋梗塞の死亡率
男女とも福島県がワースト1
福島県の男性は熊本県の4倍 女性は秋田県の5倍

福島県と全国平均の死亡率比較(2009-2019 年次推移)
以下は、政府の統計をグラフにしたものです。全国平均と福島県全体の病気ごとの死亡率を比較していますが、ここに掲載している病気はすべて全国平均より福島県の死亡率の増加傾向が顕著になっています。
(データソース)2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
*データソースの各年の表番号18(2010-2012年)12-18(2013-2019年)の「(保管表)死亡数・死亡率(人口10万対),性・死因簡単分類・都道府県別 」の数字を元にグラフを作成。








ベラルーシ科学アカデミーのミハイル・マリコ博士の言葉
「チェ ルノブイリの防護基準、年間1ミリシーベルトは、市民の声で実現されました。核事故の歴史は、関係者が事故を小さく 見せようと放射線防護を軽視し、悲劇が繰り返された歴史です。チェルノブイリではソ連政府が決め、IAEAとWHOも賛同した緩い防護基準を市民が結束し て事故5年後に、平常時の防護基準、年間1ミリシーベルトに見直させました。それでも遅れた分だけ悲劇が深刻になりました。フクシマでも早急な防護基準の 見直しが必要です」
–
最後に、チェルノブイリでも福島でも原発事故で最も大きな影響が出ている甲状腺がんの増加について、この10年の推移をまとめておきます。【2022年1月22日 追記】
‐
甲状腺がんの急増
2013/02/13 福島県甲状腺検査~3人が甲状腺がん、7人悪性疑い
2013/03/07 甲状腺がん「被曝の影響、否定出来ず」〜疫学専門家インタビュー
2013/06/06 甲状腺がん12人・悪性疑い15人〜福島県調査
2013/05/28 「避難基準の厳格化を」日本に勧告〜国連人権理事会
2013/10/24 UNSCEAR報告「健康影響ゼロ」は非科学的〜市民ら声明
2013/08/20 甲状腺がん悪性、悪性疑い43人〜福島県民健康管理調査
2013/11/13 福島県検査で甲状腺がん58人~最年少は8歳
2014/02/05 甲状腺がん悪性・悪性疑い74人〜福島健康調査
2014/05/16 甲状腺がんの子、疑い含め89人に〜福島県民健康調査
2014/06/10 リンパ節転移が多数~福島県の甲状腺がん
2014/08/25 甲状腺がんの子103人〜福島で10万人に30人
2014/09/01 「被ばくを強いられた」「避難したい」~親子86人が提訴
2014/12/23 甲状腺がん悪性・疑い112人~前回「異常なし」の子も4人
通常、子どもの甲状腺がんは、100万人に1人。未成年の甲状腺がん年間発生率も100万人に2人くらいでした。2006年統計で、甲状腺がんと診断された未成年者は「全国で46人」でした。これは「未成年2250万人に46人」であり「100万人に2.0人」ということになりますが、2014年の福島県では「37万人に58人」も甲状腺がんと診断されています。
日本の人口の1.5%ほどの福島県で、通常の全国の発生数よりも多い58人が甲状腺がんになっているという異常な増加です。
子どもの甲状腺がんで特に心配なことは「転移が早い」ということです。
福島県の県民健康調査「甲状腺検査評価部会」(平成26年11月11日)の資料によると、福島県立医大で手術した甲状腺がん54例のうちリンパ節転移は74%(40例)甲状腺外浸潤が37%(20例)と報告されています。また、鈴木眞一教授が日本癌治療学会で、「8割超の45人は腫瘍の大きさが10ミリ超かリンパ節や他の臓器への転移などがあり、2人が肺にがんが転移していた」と報告しています。

チェルノブイリ原発事故で大きな被害を受けたベラルーシの国立甲状腺がんセンターの統計では、15歳未満は3人に2人がリンパ節に転移し、6人に1人が肺に転移しています。
「がんの進行が早い子どもの甲状腺がん」は、スクリーニング検査(一斉検診)が行なわれずに、自覚症状が出てきて検査を受けた場合、がんが進行していることが多くなります。「3・11甲状腺がん子ども基金」の報告や甲状腺疾患専門病院(伊藤病院、隈病院、野口病院)の小児甲状腺がんデータでは、自覚症状が出てから検査を受けて手術する場合、左右2つある甲状腺を両方「全摘」しなければならない子どもが3倍以上に増えています。全摘すると一生ホルモン剤を飲み続けなければなりません。また、肺などへの転移や再発の比率も高くなります。
スクリーニング検査で早くがんが見つかれば、甲状腺の摘出が片方で済むことが多く、転移も少なくなります。チェルノブイリでは、年2回ほど検査してきましたが、日本では「20歳まで2年に1回」であり(空白期間に発症している例も増えています)それ以降は「5年に1回実施予定」としています。しかも、福島県以外では、こうした公的な検診をほどんど行なっていません。
2014/06/10 リンパ節転移が多数~福島県の甲状腺がん
2014/08/25 甲状腺がんの子103人〜福島で10万人に30人
2014/09/01 「被ばくを強いられた」「避難したい」~親子86人が提訴
2014/12/23 甲状腺がん悪性・疑い112人~前回「異常なし」の子も4人
2015/08/27 北茨城市検査で、小児甲状腺がん3人
福島県外(北茨城市と宮城県丸森町)でも子どもの甲状腺がん発生
–
2015/09/01 甲状腺がん疑い含め137人へ、2巡目は25人〜福島健康調査
2015/09/2 「20ミリは高すぎる」〜南相馬・避難基準裁判始まる
2015/10/09 甲状腺がん「チェルノブイリの多発傾向と酷似」〜疫学専門家
2015/11/28 甲状腺がん悪性・悪性疑い152人〜福島県民健康調査
2016/02/12 甲状腺がん悪性・悪性疑い166人〜福島県調査
2016/06/06 事故時5歳児、甲状腺がん~悪性・悪性疑い172人
2016/08/24 「甲状腺検査の拡充」求め県に要望書~家族会
2016/09/12 福島調査・甲状腺がん疑い2巡目だけで59人〜計174人
2016/12/15 甲状腺がん治療充実へ〜国内最大の治療施設完成・福島医大
2016/12/26 甲状腺がん・福島県外で重症化〜基金が初の療養費給付
2016/12/28 福島の小児甲状腺がん疑い含め183人〜2巡目で68人
福島県の甲状腺がん発表は実数より少ない
2017/03/31 184人以外にも未公表の甲状腺がん〜事故当時4歳も
2017/03/31 未公表の4歳児へ給付〜甲状腺がん子ども基金
2017/06/04 甲状腺がん190人〜公表データ以外の把握、検討へ
政府や福島県は「 事故当時5歳以下の子どもに甲状腺がんが見つかってないからチェルノブイリとは違う」と発表していましたが、NPO「3・11甲状腺がん子ども基金」が福島県の公式データには含まれていない事故当時4歳児に療養費を給付していたことから「福島県が発表している数字は、実際の人数より少ない」ことが判明しました。
2019年6月現在、甲状腺がん子ども基金 は 原発事故時2歳〜18歳の子どもたち149人に療養費を給付しています。
2017/10/04 甲状腺がん患者への支援100人へ〜7人は再手術
2017/10/20 福島の小児甲状腺がん193人に〜手術は154例
2017/12/20 「放射線の影響とは考えにくい」に疑問~甲状腺がん患者の8割
2018/03/01 福島・甲状腺がん196人〜「学校検診見直し」検討へ
2018/06/19 甲状腺がん悪性または疑い200人超え〜福島県が公表

2018/07/09 集計漏れ11人〜福島県の甲状腺がん209人へ
2018/09/04 甲状腺がん集計外含め211人〜福島県
2019/04/05 甲状腺がん悪性疑い211人〜福島県集計データ
2019/06/17 甲状腺がん子ども基金149人に給付〜福島での再発転移12人

2019/10/04 甲状腺がん疑い230人〜福島県検査で13人増加
2019/10/17 小児甲状腺がんの再発11人〜福島県立医大手術例
2020/01/31 福島の小児甲状腺がん180例を症例報告〜「過剰診断」を否定
2020/02/12 小児甲状腺がん悪性疑い236人〜福島健康調査
2020/05/22 甲状腺検査サポート事業の受給者314人~福島県
2020/06/12 甲状腺がん疑い計240人〜福島県3巡目の31人解析へ
2020/08/26 甲状腺摘出手術200人〜福島県の甲状腺検査
2021/01/14 原発事故時0歳と2歳が甲状腺がん〜福島県の健康調査
(2021年1月15日 ourplanet )より抜粋
東京電力福島第1原発事故に伴う福島県民の健康調査について議論している「県民健康調査」検討委員会が15日、福島市内で開かれた。今回初めて、事故当時0歳だった女児と2歳だった女児の二人の乳児が甲状腺がんと診断されたことが分かった。
資料 https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/kenkocyosa-kentoiinkai-40.html
2021年1月15日現在:福島県の子どもに甲状腺がんがあると診断された患者は252人に達し、このうち203人が甲状腺手術を実施。1人を除く202人が甲状腺がんと確定した。 また、この252人に含まれていない「集計外」の子どもが30人以上いることも判明しています。
【2022年1月22日 追記】
2021/03/19 福島の小児甲状腺がん275人〜がん登録で24人判明
2021/06/03 「検査に救われた」甲状腺がん患者が検査継続を訴え
2021/07/23 福島の小児甲状腺がん287人〜事故10年で1万人に6人手術
2021/08/17 「避難者調査」国連報告者の受け入れ要請〜原発事故避難者ら
2021/10/14 福島県の甲状腺がん、集計外含め293人〜星座長は5期目
※星北斗氏の擁立、正式に決定 来夏参院選で自民福島県連(2021.12.22 福島民友新聞 )
2022/1/4 (共同通信)国連報告者訪日再び要請 福島調査、調整中と外務省
2022/01/19 小児甲状腺がん患者6人、東電提訴へ〜4人は再発患者
甲状腺がんの6人、東電提訴へ 「原発事故の被曝が原因」
東京電力福島第一原発事故に伴う放射性物質の影響で甲状腺がんになったとして、17~27歳の男女6人が東電に計6億1600万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こす。27日に提訴する予定。原告側弁護団によると、住民が甲状腺がん発症による事故被害を東電に訴えるのは初めてという。
原告は2011年の原発事故時に6~16歳で、福島県内に住んでいた。県の調査などで甲状腺がんと診断され、2人は甲状腺の片側を切除、4人は再発によって全摘したという。
弁護団は19日に会見し、原告は遺伝性のがんではないと主張。がん発症で進学を諦めた原告もいて、「東電は事故との因果関係を認め、補償制度をつくるべきだ」と訴えた。子どもの甲状腺がんが事故後に県内で多発しているとも指摘した。
東電は提訴について「誠実に対応する」とコメントした。
県の調査によると、事故当時18歳以下だった県民38万人のうち、約260人が甲状腺がんかその疑いがあると診断された。ただ、県の専門委員会は15年に公表した中間報告で、事故による被曝(ひばく)とがんとの因果関係は「現時点で認められない」としている。(村上友里)
甲状腺がん26歳、肺転移も 東電提訴「今できることを」
国連報告者訪日再び要請 福島調査、調整中と外務省
(2022年1月4日 共同通信) 東京電力福島第1原発事故の避難者調査のため国連のセシリア・ヒメネス・ダマリー特別報告者(国内避難民の権利担当)が2018年から訪日を求めながら事実上放置されていた問題で、避難者を支援する全国の約80の団体が4日、外務省に再び訪日受け入れを求める要請を行った。 環境保護団体グリーンピース・ジャパンをはじめとする非政府組織(NGO)などで、代表4人が早期の訪日受け入れ決定が必要だとする要望書を外務省の担当者に手渡した。担当者からは「関係省庁と鋭意調整中だ」との回答があったという。団体は昨年8月にも訪日実現を申し入れていた。





















少し大きめ.png)
少し大きめ.png)

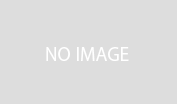

この記事へのコメントはありません。