◆原発避難者住宅 復興は支援継続にあり
(2017年1月28日 東京新聞【社説】)
福島原発事故の自主避難者向けに福島県が無償で行っている住宅支援の廃止が迫る。国策が招いた災害の被害者を強制退去などで住まいから追い出してはならない。被災者の復興は支援あってこそ。
住まいという生活の基盤を奪われてしまったらどうなるか。行き場を失う人が出る。自主避難者たちは不安を募らせている。
自主避難者は国が決めた避難指示区域の外から被ばくを避けるために県内外に避難した人たちだ。避難指示区域から避難した人たちとは違い、不動産賠償や精神的慰謝料の支払いなどはなく、経済的にも追い詰められがちだ。
その点でも福島県の判断で「みなし仮設住宅」として無償提供される住宅は役立った。災害救助法に基づく制度で最終的には国庫負担金などで全額賄われる。対象者は昨年10月時点での約1万2000世帯(約3万2000人)。賠償の蚊帳の外に置かれた自主避難者にとっては唯一の補償のようなものだ。
この支援が3月末で打ち切られようとしている。県は除染が進んだことや、食品の安全が確認されたことなどを廃止の理由に挙げているが、避難者が納得できるだろうか。県によると昨年10月時点で7割が4月以降の住居を決めていなかった。
復興庁の調査などでも分かるように、ふるさとに帰還を希望する避難者の割合は低い。若い世代ではほとんどが避難先での生活を続けることを望んでいる。子どもの生活環境をまた変えることや、汚染の残る場所に戻ることへの不安が大きいからだ。
自主避難者の団体は4月以降も住宅の無償提供を継続するよう求めているが、県は廃止方針を変えていない。避難者側に示されたのは月額所得21万4000円以下の約2000世帯への家賃補助である。
避難者は国の原発政策が招いた事故の被害者であることを忘れてはならない。一方的に支援の打ち切りを通告するのではなく、もっと被災者の思いを聞き、時間をかけて話し合うべきではないか。
避難者を受け入れてきた自治体の中には、住宅支援の必要を理解し、独自予算を組んで支援継続を表明したところもある。しかし、こうした自治体は一部であり、その努力には限りがある。
未曽有の原発事故である。国は事故翌年に議員立法で成立した「原発被災者支援法」を骨抜きにしてきたが、それは誤りだ。住まいなど被災者の生活安定に責任を持って関与するのが筋である。
http://www.tokyo-np.co.jp/…/editori…/CK2017012802000152.html
「原発事故被災者の居住保障」(視点・論点)
帝京大学 教授 山川 充夫(2017年1月23日 NHK視点論点)
原災被災地の避難指示区域は、その一部において解除が進められており、この3月には自主避難者への住宅の無償提供の打ち切りも予定されています。 しかし帰還困難区域や居住制限区域では、依然として基準値を超える放射能汚染があります。さらに中間貯蔵施設の建設と、他地域から放射性物質を含んだ除染物質が本格的に搬入され、原災避難者の「ふるさと」への帰還は進んでいません。なぜ帰還が進まないのか、その問いに対する被災者の思いは、なぜ自らに責任が全くないのに理不尽な避難生活を続けなければならないのかにあります。
深刻な問題は、家族や地域コミュニティーが繰り返し分断させられ、人間のつながりが持てないことにあります。それは自宅から避難所へ、避難所から見なし仮設を含む仮設住宅へ、仮設住宅から復興公営住宅へといった、避難生活の場所や形態を変えるたびに、子どもの教育をどこでどのように受けさせるのか、働き場所を求めつつ家族の生活をどこでどのように再建していくのか、子どもや祖父母の心身の健康や福祉・介護・医療をどこでどのように受けるのか、さらに生きがいを何に求めるのかが、強制避難・自主避難といった形態にかかわりなく、避難者には問い続けられています。これは被災者に共通した心の奥底の思いで、放射線低線量被ばくが身体にどのような影響を及ぼすのかについての考え方の違いを超えているのです。
避難者にとって現実的な困難は、目に見える売上高の減少とかハード的な社会資本の毀損とかもさることながら、目に見えにくいソーシャル・キャピタルとしての社会関係資本を失ったことにあります。「当たり前であった」ことがそうでなくなり、全てが「当たり前でない」状況のもとで孤立して生活再建を行わなければならなくなったことです。生活場所をやむを得ず移動するたびに、経済的負担とともに非経済的負担をも大きく強いられています。昨今、福島から避難した子どもへのいじめが大きく報道されました。子どもたちが「社会関係資本」としての「ふるさと」をなくし「友だち関係」を失った時、どのような状況に陥るのかを端的に表しています。大人では、将来設計の見通しがつかないことが心身をむしばんでいきます。仮設住宅での一人暮らしの高齢者は、家族やコミュニティーや生業を失ったことで生きがいを失い、自殺など「震災関連死」の増加が危惧されています。
原発災害以外の災害であれば、たとえ被災者は家族を失うなどの「悲惨な」状況にあっても、時間の経過とともに、どこかで区切りが付けられ復興に向けて前に進もうという段階がやってきます。しかし原子力災害では原発事故未収束の状況が依然と、しかも長期に及んでおり、避難生活から仮設生活へと移行するなかで新たな問題が付加されます。生活拠点を変えたからといって原災被害が終わるわけではありません。こうした累積的な被害構造という深刻な事態を念頭において、生活再建政策は講じられるべきだと考えています。
日本学術会議は原発事故や被災地域や被災者問題にかかわる学術フォーラムを行っています。私が委員長を務めた福島復興支援分科会は2014年9月に『東京電力福島第一原子力発電所事故による長期避難者の暮らしと住まいの再建に関する提言』を出しました。

ここでの『提言』のポイントは「帰還かそれとも移住か」の二者択一を原災避難者に求めるのではなく、「複線型復興」という考え方のもとで「避難継続」というもう一つの選択肢を積極的にとらえることにあります。
この『提言』は福島県が2013年度以降、継続的に実施している「福島県避難者意向調査 」からしても現実味があることがわかります。


調査結果によれば、避難者全体で「同じ市町村に戻りたい」、「現在の避難先で定住したい」、「県外に定住したい」、「現時点では決まっていない」などの回答比率は、県内外避難別や避難形態別において違いはあるものの、いずれも減少してきています。「県外に定住したい」は減っていません。ただしここで注目すべきは、「無回答」の比率が3年間で急激に上昇したことです。もちろん「無回答」をどのように理解するのかは、今後、政策論的にもきちんと議論されなければなりません。ただいえることは、「現時点では決まっていない」と「無回答」とを合わせた割合が、避難先や避難形態での違いはあるものの、依然として大きな比率を占めていることです。
国は「避難指示解除」を進め、福島県は「早期帰還プラン」や「復興計画」を進めてきています。

しかし避難者の意思が固まらないまま、こうした解除やプランや計画が進められ、しかも生活の根幹をなす住宅の無償提供が打ち切られれば、「避難継続」を望む避難者は不本意な選択をせざるを得ず、新たな「指示解除」被害ともいうべき状況を生み出しかねません。自主避難者はこれまでも家族の分断やコミュニティーからの疎外など、辛酸をなめる生活を送ってきましたが、今度は「強制避難者」が「自主避難者」化せざるをえなくなります。
私たちは先に述べた『提言』において、当面帰還を選択しない住民も「二重の住民票」 制度など行政サービスを継続して公平に受けられる市民的権利を保障する制度の必要性を訴えました。市民的権利を保障するためには、原発事故に備えた実効性のある避難計画を樹立すること、被災者の生活再建と被災地の再生、さらには放射線と健康対策に関する一連の原災対応に関わる総合的かつ包括的な、例えばウクライナなどにはあるチェルノブイリ法に相当する「原子力災害対策基本法」の制定は欠かすことができません。これは国としての原子力の「平和利用」政策の失敗にきちんと責任をとる姿勢を明確にすることでもあるのです。
とはいえ「基本法」の制定はなお時間がかかりますので、短期的には「子ども・被災者支援法」を避難者の生活実態に合わせ、柔軟な形で運用することが求められます。福島県が3年間行ってきた避難者意向調査の全データについて、世帯員数や年齢構成や性別等の属性別に詳細な分析を行うことと、生活実態に合わせ避難者一人一人へのきめ細かな支援を実現することが大切です。当面の大きな課題としては、この3月に打ち切りが予定されている自主避難者への住宅の無償提供の打ち切りについては、避難者の犠牲をこれ以上増やさないためにも、国及び福島県はそれを継続すべきであると考えます。


子どもの保養・移住先探し・各地で相談会.jpg?resize=181%2C181)




少し大きめ.png)
少し大きめ.png)
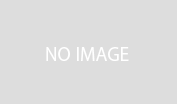


この記事へのコメントはありません。