「もうひとつのノーベル賞」とも言われるライト・ライブリフッド賞を受賞した高木仁三郎さんは、1991年発行の著書『核燃料サイクル施設批判』(七ツ森書館)で非常に重要なことを書いている。
(「第3章 厳しくなったリスク認識―放射線の人体への影響」から抜粋)
(1)つきつけられた現実
ここであえて一章を設けて、放射線の危険性についてお話をしたいのは、放射線の危険性がこれまで考えられてきたよりもはるかに深刻であるという認識が最近、専門家の間に高まってきたからです。結論を先取りしていえば、従来考えられてきたより10倍も危険と考えなくてはならなくなってきたからです。
10倍も危険性の認識を変え、さまざまな規制値を10倍(10倍でもまだ甘すぎるかもしれないのですが)も厳しくする(10分の1に切り下げる)としたら、核燃料サイクル施設のほとんどの事業が成り立たなくなるでしょう。ですから、推進側には、上の危険性の認識が定着し、日本の法令にも取り入れざるを得なくなる前に――専門サイドにもすでにそういう厳しい規制を避けようとするさまざまな策動があるのです――、六ケ所の基本計画をすべて通してしまいたい、という焦りのようなものが感じられます。
国際放射線防護委員会(ICRP)などが考えたり、勧告したりしているよりも、放射線の危険性ははるかに大きいに違いないと考えていた人は以前から大勢いたのです。もちろん、科学者の中にも、一部そのような人たちがいましたが、その人たちは少数派で、またそういう研究結果を発表したりした人のほとんどが、研究費をカットされたり、職を追われたりしてきました。しかし、そういう人たちよりもはるかに多くの人たちが、実は放射線が各国政府の言い分などよりも、はるかに危険であることを知っていました。それは、ビキニの核実験の死の灰を浴びたマーシャルの人たちであり、アメリカやカナダやオーストラリアのウラン鉱山労働者(その多くは先住民)であり、ソ連のセミパラチンスクやチュコト半島の核実験の被害者でした。
実際に、そういうひとたちの現実を調査し、その声を科学的にデータとしてまとめた科学者も何人かいます。有名なのは、1970年半ばに公表されたアメリカのマンクーゾ博士の仕事です。マンクーゾは、イギリスのスチュアート博士やニール博士の協力を得て、ハンフォード原子力施設の労働者の健康被害を調査し、放射線に被曝してがんによって死ぬ危険性(リスク)は、従来ICRPなどが主張してきたものより少なくとも10倍から20倍は高いという結果を得ました。彼は”許容量”は少なくとも10分の1に切り下げられるべきであることを主張しましたが、研究費をカットされ、研究は別の人にとって代わられてしまいました。
ほかにも少なからぬ科学者がいますが、最も有名なのは、アメリカのゴフマン博士でしょう。彼も、独自の研究から放射線によるがん死のリスクはICRPなどの考えるより30~40倍も大きいという結論に達したのですが、各国の政府や、ICRP、国連科学委員会(UNSCEAR)などは、すべてこういう人たちの研究成果を無視してきたのが、この十数年の歴史です。
世界中の被害住民が肌で感じてきたことが誤りだったのか、それとも原子力産業と密着したICRPの側に重大な誤認があったのか、実はこの論争に思わぬところから、被害住民に強力な援軍が現れ、決着がつけられることになったのです。その援軍とは、ほかならぬ広島、長崎の被害の見直し(とくにがん死と放射線の関係)は、従来の認識の甘さをはっきりと示すことになったのです。
(2)広島・長崎の再評価
これまで、ICRPなどが放射線の危険性評価の基準としてきたのは、なんといっても広島・長崎の被爆者の調査データに基づくものです。
ところが、1970年代末頃から、それまで最も信頼のおけると考えられてきた原爆投下時の放射線量(各人の被ばく線量)のデータの集積T‐65D(1965年の暫定線量評価=米オークリッジ研のオークシャーらによる)が、どうも相当あやしいという意見が強く出され、全面的な見直しが進められました。広島にある放射線影響研究所を中心に日米の合同委員会で進められた評価は、1986年に公表されDS‐86と呼ばれています。
DS‐86は、T‐65Dがまったくの誤りであったことを明らかにしました。広島や長崎の被爆データから放射線の危険性を推測する場合、
(A)被爆者の浴びた線量を正確に知る。
(B)その被爆者の間にどのようながんがどのように発生しどのくらい死亡したかを知る。
の2つの要素が、必要です。AとBの関連づけから、放射線の危険性がわかるのです。ところが、上のいきさつで、Aの方が従来とはまるで(極端な場合には一桁以上も)違うことがわかりました。
問題はそれだけでなく、1965年のT‐65D当時と比べ、Bの方の調査も広島や長崎の医師の協力を得て前記の放影研によって、ずいぶん進められ、寿命調査10、11、といった資料がまとめられました。これらによって、1985年までの被爆者のがん死の全体像がほぼつかめました。
その結果は、従来考えられていたよりも、被爆者の間にがんの発生が長期にわたって(現在でも)持続し、とくに最近においては若年時被爆者(若いとき、幼いときに被爆した人が現在”がん年齢”を迎えつつある)の間に、がん死が多くみられることがわかりました。
これらの結果を数字的にまとめると「放射線は10倍危険」説をピタリと裏づけることになったのでした。
放影研の研究結果は、1988年の国連科学委員会報告でも、かなりの程度に認めざるを得なくなりました。また、1990年初めに出されたアメリカの科学アカデミーのもとのBEIR-V報告(「電離放射線の生物学的影響に関する委員会」の第5報告)でも基本的に放影研の結果を認めています。
(3)産業界の利益についたICRP
こうなるといままで世界各国に放射線規制の勧告を出してきたICRPとしても、現在の各国の基準のもとになっているICRPの1977年勧告(ICRP公報26)の全面的見直しに迫られます。この1977年勧告は、日本でも法体系の中に1989年から組み入れられていて、その要点は、
職業人(放射線従事者)の年線量限度(”許容量”)=50ミリシーベルト
公衆(一般人)の年線量限度=1ミリシーベルト
というものです。一般人と職業労働者の間に50倍も差があるのに驚かされますが、労働者は専門的な監視下に置かれているからそれでよい(実際は労働者の規制をあまり厳しくしては原子力産業が成立しない)というのです。
放射線の認識がこの間どれだけ変わったか、表に示しておきます。
これはこの十数年間の公的機関が出した、がん死の危険性(リスク)に対する評価値を表にしたもので、数字に幅があるのは、いろいろな数式モデルの解釈があるためです。しかし、この表でも、上に述べてきたような認識の変遷は明白でしょう。
表の1万人シーベルト当たりというのは、被曝者の総線量を足し合わせた数が1万人シーベルトになると、という意味です。すなわち、1人10ミリシーベルトずつ100万人浴びても、100ミリシーベルトずつ10万人浴びても、また20,000人の人が50ミリシーベルトずつ10年間浴びても、その合計は1万人シーベルトとなります。
この表はちょっとややこしいですが、1977年から1990年まで、いかにリスク評価が増したかは、一目瞭然でしょう。一番下の1990年のICRPの評価(これは政治的配慮が濃い)を別にすれば、この十数年あまりで”10倍厳しくなった”と言ったことに、少しの誇張もないことがわかるでしょう。
イギリスの放射線防護庁の委員会などは、このような結果を踏まえて、労働者の年線量限度(許容線量)を15ミリシーベルト(30%)に、一般人を0.5ミリシーベルト(50%)に切り下げるべきだと勧告しています。これはいわば当然の流れでしょう。
さすがに、ICRPもこの事情を反映せざるを得なくなり、最近1990年勧告案を公表しました。誰しもが1977年勧告より大幅に厳しい規制値の勧告が出ると期待したのです。ところが何とその結果は、
労働者の年50ミリシーベルトはの限度はそのまま
一般人の年1ミリシーベルトの限度もそのまま
ただし、労働者に限って、5年間で100ミリシーベルトという制限をつける、ということのようです。(年平均にすると20ミリシーベルト)
結局、これだけの事実を前にしながら、ICRPは産業界の利益の側について、甘い規制を死守しようというのでしょう。こんなことは世界で通用せず、早晩、90年勧告は再度の書き直しを迫られると思いますが、それまでの間の時間稼ぎがねらいかもしれません。
本来の事実に基づき、規制値を10分の1以下に切り下げ強化したら、核燃料施設を含めてほとんどの原子力施設は、存在しえなくなるでしょう。例えば、1989年度のデータで、10ミリシーベルト以上の被曝をした原発労働者は、日本全体に2012人、5ミリシーベルト以上では5602人もいるのですから。
*高木仁三郎著『核燃料サイクル施設批判』(七ツ森書館)P40ーP46
1991年1月21日 初版第1刷発行
◆高木仁三郎(ウィキペディア)から抜粋
(たかぎ じんざぶろう、1938年7月18日 – 2000年10月8日)は、日本の物理学者、専門は核化学。理学博士(東京大学)。群馬県前橋市出身。東京大学理学部化学科卒業。
政府の原子力政策について自由な見地からの分析・提言を行う為、原子力業界から独立したシンクタンク・原子力資料情報室を設立、代表を務めた。原子力発電の持続不可能性、プルトニウムの危険性などについて、専門家の立場から警告を発し続けた。特に、地震の際の原発の危険性を予見し地震時の対策の必要性を訴えたほか、脱原発を唱え、脱原子力運動を象徴する人物でもあった。
略歴
- 1961年、日本原子力事業(日本原子力事業総合研究所核化学研究室)に勤務。
- 1965年、東京大学原子核研究所助手となる。
- 1969年、東京都立大学理学部助教授。
- 1972年、マックスプランク核物理研究所客員研究員。
- 1975年、原子力資料情報室専従世話人となる。(のちに、代表)
- 1992年、多田謡子反権力人権賞受賞。
- 1993年、サンケイ児童出版文化賞受賞。
- 1997年、ライト・ライブリフッド賞(Right Livelihood Award)受賞。
- 2000年、大腸癌で死去。12月、遺志により高木仁三郎市民科学基金が設立される。
地震による原子力災害への警鐘
1995年、『核施設と非常事態 ―― 地震対策の検証を中心に ――』[1] を、「日本物理学会誌」に寄稿。「地震」とともに、「津波」に襲われた際の「原子力災害」を予見。
「地震によって長期間外部との連絡や外部からの電力や水の供給が断たれた場合には、大事故に発展」[1] するとして、早急な対策を訴えた。
福島第一原発 について、老朽化により耐震性が劣化している「老朽化原発」であり、「廃炉」に向けた議論が必要な時期に来ていると (1995年の時点で)指摘。 加えて、福島浜通りの「集中立地」についても、「大きな地震が直撃した場合など、どう対処したらよいのか、想像を絶する」と [1]、その危険に警鐘を鳴らしていた。






少し大きめ.png)
少し大きめ.png)

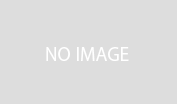

この記事へのコメントはありません。