
福島の子ども、甲状腺がん「多発」どう考える 津田敏秀さん・津金昌一郎さんに聞く
(2015年11月19日 朝日新聞)から抜粋
■原発事故の影響、否定できぬ 津田敏秀さん 岡山大大学院教授(環境疫学)
福島県の甲状腺検査は1巡目のデータ解析でも、国立がん研究センターの統計による全国の19歳以下の甲状腺がんの年間発生率と比べ、検査時点でがんと診断された人の割合は県央部の「中通り」で約50倍、県全体でも約30倍の「多発」となる高感度の機器で一斉に調べれば自覚症状のない隠れたがんも見つかるため、それを補正して比較した数値だ。一斉検査での「増加」は過去の報告の分析でも数倍程度。福島は桁が違う。多発は県の検討委員も認めざるを得なくなってきた。
「生涯発症しないような成長の遅いがんを見つけている」という「過剰診断」説もある。だが、これほどの多発は説明できない。過剰診断説を採ると、100人以上の手術が不適切だったことになってしまう。県立医大の報告では、同病院で手術を受け、がんと確定した96人のうち4割はがんが甲状腺の外に広がり、7割以上がリンパ節に転移していた。
逆に、多発と原発事故との関連を否定するデータはない。事故直後に放射線量が高かったと見られる県央部や原発周辺自治体ごとのがんの人の割合、事故から検査までの期間をふまえて解析してみると、被曝(ひばく)量と病気の相関関係、つまり「量―反応関係」も見えてくる。
県は、チェルノブイリ原発事故では4~5年後から乳幼児で増えたのに対し、福島では10歳以上に多いなど、違いを強調する。しかし、ベラルーシやウクライナの症例報告書を見ると、チェルノブイリ事故の翌年から数年間は10代で増えているなど、福島と驚くほど似ている。
福島で放出された放射性ヨウ素はチェルノブイリの10分の1とも言われるが、いかに低線量でも人体に影響があるとの考え方は国際機関に認められている。人口密度が高ければ影響を受ける人は増える。福島や北関東の人口密度はチェルノブイリ周辺の何倍もあり、多発の説明もつく。
予想される甲状腺がんの大発生に備えた医療体制の充実が必要だ。甲状腺がんは初期の放射性ヨウ素による内部被曝だけが原因ではなく、他の放射性物質からの外部被曝の影響を示す研究もある。甲状腺がんだけでなく、すべてのがんへの影響を考えれば、妊婦や乳幼児には保養や移住も有意義だ。放射線量が高い「避難指示区域」への帰還を進める政策は延期すべきで、症例把握を北関東にも成人にも広げる必要がある。
県の検討委は、甲状腺がんは成長が遅いというが、子どもの場合の実際のデータは違う。 県の検査でも、1巡目で見つからなかったがんやがんの疑いが、2巡目で25人(※9月30日現在39人)も見つかった。すべてが1巡目での見落としではな いだろう。「放射線影響は考えにくい」とは言えない。
科学の役割は、データに基づいて未来を予測し、住民に必要な施策を、手遅れにならないように提案していくことにある。
福島の小児甲状腺がん「被曝による発生」〜医学誌に論文
福島県で実施されている小児甲状腺検査の結果データを分析した論文が、国際環境疫学会の発行する「医学雑誌「エピデミオロジー(疫学)」での掲載が決まり、オンライン上で先行公開された。福島で起きている小児甲状腺がんの多発は「スクリーニング効果」や「過剰診断」ではなく、「被ばくによる過剰発生」であること結論づけている。
http://journals.lww.com/epidem/Abstract/publishahead/Thyroid_Cancer_Dete…
 論文のタイトルは「2011年から2014年の間に福島県の18歳以下の県民から超音波エコーにより検出された甲状腺がん」。著者は岡山大学の津田敏秀教授らのチームが、福島県が実施している小児甲状腺検査の結果データのうち、昨年12月31日までに判明した結果を疫学的な手法で解析した。
論文のタイトルは「2011年から2014年の間に福島県の18歳以下の県民から超音波エコーにより検出された甲状腺がん」。著者は岡山大学の津田敏秀教授らのチームが、福島県が実施している小児甲状腺検査の結果データのうち、昨年12月31日までに判明した結果を疫学的な手法で解析した。
福島県の甲状腺検査は、原発事故当時、18才未満だった約38万人を対象に実施しているもので、2011年度から13年度を1巡目、2014年度〜15年度を2巡目と位置づけている。論文ではまず1巡目で、甲状腺の超音波スクリーニング検査を受診した子ども約30万人の検査結果を分析。潜伏期間を4年と仮定して日本全国の年間罹患率と比較した場合、最も高い発生率比(IRR)を示したのは、福島県中通りの中部(福島市と郡山市の間)で50倍、全体としても約30倍程度の多発が起きていることを明らかにした。また、地域によって多発の割合が異なっていると指摘している。


さらに論文では、2巡目で甲状腺がんが8例出ていることについても検討。この時点で診断が確定していない残りの受診者から一例も甲状腺がんが検出されないという仮定しても、すでに12倍の発生率比が観察されていると分析した。2巡目で甲状腺がんと診断された子どもたちのほとんどは、1巡目の検査では2次検査を必要とするしこりなどは観察されていなかった。
研究チームはこれらの分析により、福島の子どもの甲状腺がんは、事故後3年目以内に数十倍のオーダーで多発しており、スクリーニング効果や過剰診療など、放射線被ばく以外の原因で説明するのは不可能であると結論づけている。
国際環境疫学会の発行する医学雑誌「エピデミオロジー(Epidemiology)は、疫学分野のトップジャーナルの一つとして知られており、環境曝露の人体影響や疫学理論の分野で影響力がある。福島県の小児甲状腺検査結果を疫学的に分析した論文が、査読つきの国際的な医学雑誌に掲載されるのは初めてとなる。
<論文情報等>
2011年から2014年の間に福島県の18歳以下の県民から超音波エコーにより検出された甲状腺がん 全文PDF
著者
津田敏秀(岡山大学大学院環境生命科学研究科・人間生態学講座)、
時信亜希子(岡山大学大学院医歯薬学総合研究科・疫学衛生学講座)
山本英二(岡山理科大学情報学部・情報科学講座)
鈴木越治(岡山大学大学院医歯薬学総合研究科・疫学衛生学講座)
アブストラクト(和訳)
背景:2011年3月の東日本大震災の後、放射性物質が福島第一原子力発電所から放出され、その結果として曝露された住民に甲状腺がんの過剰発生が起こるかどうかの関心が高まっていた。
方法:放射性物質の放出の後、福島県は、18歳以下の全県民を対象に、超音波エコーを用いた甲状腺スクリーニング検査を実施した。第1巡目のスクリーニングは、298,577名が受診し、第2巡目のスクリーニングも2014年4月に始まった。我々は、日本全体の年間発生率と福島県内の比較対照地域の発生率を用いた比較により、この福島県による第1巡目と第2巡目の2014年12月31日時点までの結果を分析した。
結果:最も高い発生率比(IRR)を示したのは、日本全国の年間発生率と比較して潜伏期間を4年とした時に、福島県中通りの中部(福島市の南方、郡山市の北方に位置する市町村)で、50倍(95%信頼区間:25倍-90倍)であった。スクリーニングの受診者に占める甲状腺がんの有病割合は100万人あたり605人(95%信頼区間:302人-1,082人)であり、福島県内の比較対照地域との比較で得られる有病オッズ比(POR)は、2.6倍(95%信頼区間:0.99-7.0)であった。2巡目のスクリーニングでは、まだ診断が確定していない残りの受診者には全て甲状腺がんが検出されないという仮定の下で、すでに12倍(95%信頼区間:5.1-23)という発生率比が観察されている。
結論:福島県における小児および青少年においては、甲状腺がんの過剰発生が超音波診断によりすでに検出されている。
◆甲状腺がん「チェルノブイリの多発傾向と酷似」〜疫学専門家
(2015年10月8日 OPTV)
福島県内の子どもの甲状腺がんが多発している問題で8日、岡山大学の津田敏秀教授が外
詳細はこちら http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/1989



.jpg?resize=181%2C181)
.jpg?resize=181%2C181)


少し大きめ.png)
少し大きめ.png)
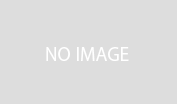


この記事へのコメントはありません。