
先月(2016年2月15日)報道ステーションは、通常、未成年者にはほとんど見られない甲状腺がんとがんの疑いが、福島県の子どもたち(原発事故当時18歳以下)167人に見つかったことを報じています。117人が手術を受けて、1人が良性で116人が悪性と判明しています。(2011年から昨年4月末までの「1巡目の検査」で、がん100人、がんの疑い15人(合計115人)、 2014年4月からの「2巡目の検査」では、受診率が低下しているにもかかわらず、昨年末現在で、がん16人、がんの疑い35人(合計51人)が見つかっている)
福島の甲状腺がんの概要を理解するために、津田敏秀教授の話からお聞き下さい。
福島の子ども、甲状腺がん「多発」どう考える 津田敏秀さん・津金昌一郎さんに聞く
(2015年11月19日 朝日新聞)から抜粋
■原発事故の影響、否定できぬ 津田敏秀さん 岡山大大学院教授(環境疫学)
福島県の甲状腺検査は1巡目のデータ解析でも、国立がん研究センターの統計による全国の19歳以下の甲状腺がんの年間発生率と比べ、検査時点でがんと診断された人の割合は県央部の「中通り」で約50倍、県全体でも約30倍の「多発」となる。高感度の機器で一斉に調べれば自覚症状のない隠れたがんも見つかるため、それを補正して比較した数値だ。
一斉検査での「増加」は過去の報告の分析でも数倍程度。福島は桁が違う。多発は県の検討委員も認めざるを得なくなってきた。「生涯発症しないような成長の遅いがんを見つけている」という「過剰診断」説もある。だが、これほどの多発は説明できない。過剰診断説を採ると、100人以上の手術が不適切だったことになってしまう。県立医大の報告では、同病院で手術を受け、がんと確定した96人のうち4割はがんが甲状腺の外に広がり、7割以上がリンパ節に転移していた。
逆に、多発と原発事故との関連を否定するデータはない。事故直後に放射線量が高かったと見られる県央部や原発周辺自治体ごとのがんの人の割合、事故から検査までの期間をふまえて解析してみると、被曝(ひばく)量と病気の相関関係、つまり「量―反応関係」も見えてくる。
県は、チェルノブイリ原発事故では4~5年後から乳幼児で増えたのに対し、福島では10歳以上に多いなど、違いを強調する。しかし、ベラルーシやウクライナの症例報告書を見ると、チェルノブイリ事故の翌年から数年間は10代で増えているなど、福島と驚くほど似ている。
福島で放出された放射性ヨウ素はチェルノブイリの10分の1とも言われるが、いかに低線量でも人体に影響があるとの考え方は国際機関に認められている。人口密度が高ければ影響を受ける人は増える。福島や北関東の人口密度はチェルノブイリ周辺の何倍もあり、多発の説明もつく。
予想される甲状腺がんの大発生に備えた医療体制の充実が必要だ。甲状腺がんは初期の放射性ヨウ素による内部被曝だけが原因ではなく、他の放射性物質からの外部被曝の影響を示す研究もある。甲状腺がんだけでなく、すべてのがんへの影響を考えれば、妊婦や乳幼児には保養や移住も有意義だ。放射線量が高い「避難指示区域」への帰還を進める政策は延期すべきで、症例把握を北関東にも成人にも広げる必要がある。
県の検討委は、甲状腺がんは成長が遅いというが、子どもの場合の実際のデータは違う。 県の検査でも、1巡目で見つからなかったがんやがんの疑いが、2巡目で25人(※2月15日現在51人)も見つかった。すべてが1巡目での見落としではな いだろう。「放射線影響は考えにくい」とは言えない。 科学の役割は、データに基づいて未来を予測し、住民に必要な施策を、手遅れにならないように提案していくことにある。
******朝日新聞の記事の転載はここまで******
甲状腺がんの多発は「過剰診断によるものだからスクリーニング検査は止めた方がいい」と主張する「専門家」もいますが、2014年8月に開かれた日本癌治療学会で、甲状腺がんと確定した子ども57人のうち県立医大が手術した54人について、8割超の45人は腫瘍の大きさが10ミリ超かリンパ節や他の臓器への転移などがあり、診断基準では手術するレベルだったこと。そして、2人が「肺にがんが転移」していたことを報告しています。
もしも、甲状腺検査をしていなかったら、この子たちはどうなっているのでしょうか?
そのヒントになる記事があります。
原発事故当時、中学3年生だった女性が取材に応じています。
◆福島原発事故後に甲状腺ガン 20歳女子の悲痛な日々
2度の手術も、リンパや肺に転移。弟2人も甲状腺にのう胞が…
(2015年9月25日号 FRIDAY)から抜粋
取材・文/明石昇二郎(ジャーナリスト)
「小児甲状腺ガンという診断をうけたときは、『えっ!? なにそれ』という感覚でした。それまでなんの自覚症状もなかったんですから。ガンがリンパや肺にも転移し、その後2回も手術を受けることになるとは思っていませんでした」
こう明かすのは福島県中部(中通り地方)に住む、20歳の女性Aさんだ。
8月31日の福島県の発表によると、11年3月の福島第一原発事故発生当時18歳以下だった県民36万7685人のうち、甲状腺ガン、またはその疑いがあるとされた人は137人。発症率は10万人あたり37.3人で、通常の100倍近くも高い。とくに左ページ下の地図で示した「汚染17市町村」の発症率は 10万人あたり42.9人で、ガンが見つかったAさんも同地区内で悲痛な日々を過ごしている――。
東日本大震災が起きた当日は、Aさんの中学校の卒業式だった。原発事故直後の3日間は外出をひかえていたものの、その後は通常の生活を続けていたという。 「県立高校への進学が決まっていました。事故から1週間後には、制服を注文するため母と一緒にJR福島駅前にあるデパートに出かけたんです。高校入学をひ かえ た子どもたちが押しかけ、デパートは超満員。建物の外にまで行列がのび、私たちも30分ほど屋外で待たされました」(以下、ことわりのない発言はAさん)
当時は県内の空間放射線量が非常に高く、福島市内では毎時約10マイクロシーベルトを記録していた。そうした事実を知らされず、Aさんはマスクをつけずに外出していたのだ。
通い始めた大学も再発で退学
翌 年の夏休み。自宅近くで行われた県の甲状状検査で、Aさんに異常が見つかる。県からは「福島県立医大で精密検査をお願いします」との通知が届く。「ノドが 少し腫れていましたが、自分で気づかなかった。県立医大で2回目の精密検査を受けたときに医師から『深刻な状態だ』と告げられ、ガンであることがわかった んです。高校3年の夏休みに手術を受け、甲状腺の右半分と転移していた周囲のリンパ組織を切除しました」
だが、これで終わりではなかった。高校で美術部に所属していたAさんは「ウェブデザイナーか学芸員になりたい」という夢を持ち、卒業後、県外の芸術系大学に進学。入学後の健康診断で「血液がおかしい」との結果が出たのだ。「夏休みに帰郷し、県立医大で検査を受けると『ガンが再発している』と言われたんです。治療に専念するため、通い始めたばかりの大学も退学せざるをえませんでした。10月の再手術では、残っていた左半分の甲状腺とリンパ組織を切除。甲状腺は全摘出することになったんです。肺への転移も判明し、術後しばらくはかすれた声しか出ず、キズの痛みをこらえながらリハビリを続けていました」
生理不順にもなりホルモン剤を投与。今年4月には肺がん治療の ため「アイソトープ治療」も受けた。放射性ヨウ素の入ったカプセルを飲み、転移したガン細胞を破壊するという療法だ。「カ プセルを飲む2週間ほど前から食事制限があり、大好きなお菓子も食べられません。飲み物は水だけ。カプセルを飲んだ後も3日間の隔離生活を強いられます。 強い放射能のため周囲の人が被曝する可能性があるからです。お風呂に入るのも家族で最後。医師からは『トイレの水も2回流すように』と言われました」
Aさんは4人兄弟の長女で、弟2人も「甲状腺にのう胞がある」との診断を受けている。だが県立医大の担当医は、発病と原発事故との因果関係は「考えにくい」としか言わない。
疫学と因果推論が専門の岡山大学大学院、津田敏秀教授が解説する。「もっとも空間線量が高かった時期に、福島県では県立高校の合格発表が屋外で行われていました。生徒も線量の高さを知らされず無用な被曝をしていた。Aさんが暮らしている場所は、住民が避難していない地域で最大レベルの甲状腺ガン多発地域です。Aさんのケースも原発事故の影響である確率が非常に高い」
************** 記事の転載は以上 **************
福島県の青少年世代に毎年、甲状腺がんが増えているのがよくわかります。
(2015年8月発表分まで)
ここまでは、若い世代を見てきましたが、甲状腺がんは大人世代にも全国的に増えてきています。
◆甲状腺がんは子どもだけでなく、大人にも増えている
大人も含む「甲状腺がんの手術数」を原発事故前の2010年と事故後の2013年を「DPC対象病院」で比較すると、九州・沖縄の甲状腺がん「手術数」の増加は 1.07倍の増加ですが、南関東では 1.52倍、北関東では 1.83倍、東北では 2.18倍、そして 福島では 2.78倍に増加しています。(福島県の2.78倍には、子どもたちのスクリーニング検査の数字は入っていないようです)
九州・沖縄 1.07倍<南関東 1.52倍<北関東 1.83倍<東北 2.18倍< 福島 2.78倍
東北地方の「甲状腺がんの手術数」は、以下のように増加してきています。
*元データ(2010年度〜2012年度 2013年度)
・
関東地方の「甲状腺がんの手術数」は、以下のように増加してきています。
東京は人口が多いので、手術数も多く目立ちます。逆に群馬は人口が少ないので目立ちにくいのですが、2010年と2013年の手術数を比較すると2.88倍に増えています。茨城も2.26倍と多く、東京は1.62倍、関東全体は1.55倍となっています。
九州地方の「甲状腺がんの手術数」は、以下のように推移してきています。どの県も右肩上がりではありません。
.jpg?resize=611%2C323) (大分県には、甲状腺がん治療実績で全国2位の野口病院がある)
(大分県には、甲状腺がん治療実績で全国2位の野口病院がある)
九州、近畿、関東、東北は、それぞれ次のように推移しています。
東北と関東だけ増え続けています。
◆福島原発事故後に甲状腺がんだけでなく心臓病も増えています
こうした記事からも分かるように、甲状腺がんは福島県に近いエリアほど増えており、子どもだけでなく、青年にも大人にも増えてきています。また、甲状腺がんだけでなく、チェルノブイリで増えた心臓病をはじめ血管や血液など様々な病気が増え始めています。ところが日本政府は、こうした事実を直視せず、チェルノブイリから学ぼうともせず、逆に「年間20ミリシーベルト以下の被ばくなら安全」と勝手に決めつけて、原発事故以前の「被ばく限度」であった「年間1ミリシーベルト」という国際基準に戻さず、避難していた住民を汚染地に戻し続けています。

チェルノブイリ原発事故から5年後、ウクライナでは「チェルノブイリ法」を制定して、年間被ばく線量が1~5ミリシーベルトの地域では住民に移住の権利が与えられ、移住を選んだ住民に対して国は、移住先での雇用を探し、住居も提供、引越し費用や移住によって失う財産の補償も行われました。

.jpg?resize=516%2C340)



.jpg?resize=422%2C211)


.jpg?resize=399%2C224)
.jpg?resize=616%2C323)
.jpg?resize=522%2C158)



.jpg?resize=181%2C181)

.jpg?resize=181%2C181)

.jpg?resize=181%2C181)

少し大きめ.png)
少し大きめ.png)

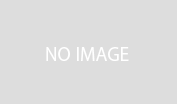

この記事へのコメントはありません。